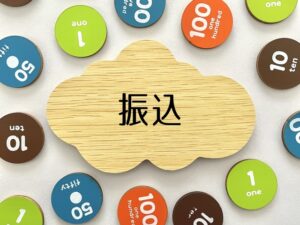「年末にお寺へ挨拶に行くとき、お布施は必要?金額はどれくらい?」と迷う方は多いものです。
この記事では、年末年始のお布施の金額相場や正しいマナーをわかりやすく解説し、現代的なお寺との付き合い方も紹介します。
年末年始のお寺への挨拶は必要?お布施のマナーとは?
日本には檀家制度というものがあり、誰もが菩提寺があり、どこかのお寺の檀家です。現在は核家族化や少子化が進んでいるため檀家離れが進んでいます。
現代的な宗教観や価値観の変化を踏まえて、お寺側も柔軟に対応するところが増えており、檀家でなくても葬儀や法事などの法要を依頼できる場合もあります。
檀家という意識が薄くても、お世話になったお寺には日ごろから挨拶に伺うのは大切なこと。
特に、お盆や年末年始にお寺へ挨拶に伺うことは必要なことです。
お盆などは期間が決まっていますので、お参りのときに挨拶に伺うのが良いでしょう。ですが、年末年始はいつ伺ったらよいか悩みますよね。
調べたところによると、厳密に「いつからいつまでに」という決まりはないようです。
年末の場合、12月31日はお寺で除夜の鐘を鳴らすので檀家や近所の人たちも大勢集まります。なので、このときに僧侶への挨拶を済ませると良いかもしれませんね。
また、年始の場合はお寺の行事で新年の集いをするところもあるので、その日程に合わせて伺うのも良いかと思います。
できれば、松の内の1月7日頃までに伺えるのが理想ですが、難しい場合は1月上旬までに伺うように心がけましょう。
さて、お寺へ挨拶に伺うときに、日ごろの感謝の気持ちとしてお布施を包む方もいるかと思います。
宗教によって異なるかもしれませんが、一般的にいくらぐらい包むのが相場なのか、調べてみました!今回は年末年始のお布施の金額相場とマナーを少しご紹介します。
年末のお寺への挨拶 金額相場
年末にお寺へ挨拶に伺うとき、お布施を持っていかれる方もいると思いますが、包む金額の相場は、一般的に3000円~5000円で、ほとんどの方は3000円としているようです。
また、お布施をお渡しするときの袋は、人それぞれのようですが、熨斗袋が適当かと思います。中には白封筒でも問題ないとしている方もいます。
ただし、お渡する袋の表書きを少し注意が必要。
年末の挨拶でお渡しするのであれば、「お布施、御布施」「お礼、御礼」「ご挨拶、御挨拶」と書くのが良いでしょう。
特別に渡すときのマナーというのはないようですが、御布施をお渡しする意味によって、表書きが変わるということを注意してくださいね。
年始のお寺への挨拶 金額相場
お正月の挨拶なのでお布施を包む熨斗袋の表に「御年賀」と書きます。
「お布施」でも問題ないようですが、年始の挨拶なので、ぜひ「御年賀」と書いてみましょう。
また、お寺は「お布施」とよく書くと思いますが、「お布施」は葬式や法事などの儀式を行っていただくときの表書きとなりますのでご注意を。
次に「御年賀」としての金額相場ですが、年末と同様に、3000円~5000円が一般的。
その中でも3000円が相場といわれています。
年末年始への挨拶に行くことは、代々続くお寺との関係が維持するために必要なことだと思います。
檀家やそうでなくても、法事や法要などでお世話になることがありますので、お気持ちとして年末年始の挨拶でお布施を納めるのは良いかと思います。
マナーについては、年末年始のご挨拶であれば、熨斗袋に書く表書きの書き方を注意しておくと良いです。
特に、中袋に書く金額の書き方ですが、これは「金壱萬圓」「金参仟圓」と旧字で書くようにしましょう。
お寺に納める金額が意外に少ないと感じた方もいるかもしれませんが、法要などで別に包むことになりますので、毎年ある年末年始では無理のない金額で問題ありません。
最近は、お寺に直接お布施の金額を聞いてしまうのも有りとされています。
心配な方はお付き合いのある僧侶に相談してみてください。
築地本願寺ラウンジ (HP:https://tsukijihongwanji-lounge.jp/)
歴史ある築地本願寺(浄土真宗本願寺派)では、人々のニーズに寄り添い、お寺の役割の利便性を高めたといわれています。
特別版!新時代、お寺とのお付き合いの仕方についてご案内年末年始にお布施を渡すときの実践マナー
渡すタイミング
年末は除夜の鐘の際、年始は松の内(1月7日頃まで)を目安に挨拶に伺うのが一般的です。ただし、どうしても伺えない場合は郵送で「御挨拶」と添え書きをしてお布施を送るケースも増えています。
表書きの注意点
・年末に渡す場合:「御布施」「御礼」「御挨拶」
・年始に渡す場合:「御年賀」
と使い分けましょう。表書き次第で意味が変わってしまうため、軽視しないことが大切です。
持参時のマナー
直接伺うときは袱紗(ふくさ)に包み、僧侶へ丁寧に両手で渡します。金額を口にする必要はなく、「今年もお世話になりました」「本年もよろしくお願いいたします」と感謝を添えて渡すのが基本です。
日本のお寺の数は全国で7万以上あるといわれています。
実はコンビニよりも多い。
でも、現代は昔と違い習慣や生活スタイルも変わり、昔ほどお寺へ行くことが少なくなっているのではないでしょうか。
かつて、日本人は各家が菩提寺を持ち、必ずどこかのお寺の檀家だった時代がありました。
もちろん現代も檀家制度が根付いているところもあると思いますが、昔に比べたら檀家制度への理解や習慣は軽薄してるといえるでしょう。
先祖代々のお墓を守るのも大変ですし、葬儀のときの高額なお布施や寄付金も納得できないという方も多いそうです。
そんな新しい時代にお寺とどうお付き合いできるかと考えたい方はぜひ参考にしてみてください。
新時代のお寺の在り方をご紹介
葬儀や法事、お墓の相談だけでないのが現代のお寺。
閉鎖的なイメージから新たなお寺像を展開しているところもあります。
築地本願寺ラウンジ (HP:https://tsukijihongwanji-lounge.jp/)
歴史ある築地本願寺(浄土真宗本願寺派)では、人々のニーズに寄り添い、お寺の役割の利便性を高めたといわれています。
新時代の交流場としてのお寺改革
令和の新時代だからこと、お寺の在り方も時代にとらわれない斬新的なお寺改革をすすめているところがあります。今回、ご紹介するのは「お寺ステイ」というプログラムです。
年末のお寺へのお布施は必要?【まとめ】
お寺に関することは実は意外にもあまりルールがないことが分かりました。お布施を渡すときのマナーはありますが、それも場面によって変わってきます。
お布施で包む金額相場ですが年末年始の挨拶の場合は、3000円~5000円が相場とのことでした。ですが、今回の内容はあくまでも強制的ではなく一般的なもので決まったものではありません。
どんなときでもお布施は、納めるその人の気持ちが大切だということを覚えておいてくださいね。
また、檀家離れのこの時代に、今後お寺とどのようにお付き合いしていくべきか新時代のお寺の在り方について調べてみました。
色々なサービスを実施しているところもありますので、
ぜひ新しい交流を求めている方がお寺ステイなどに挑戦してみてくださいね。