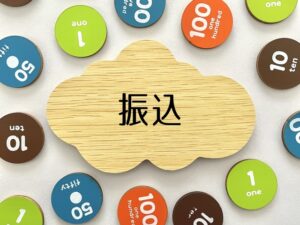大晦日は夜更かしして過ごすのが当たり前?実は「早く寝るのは縁起が悪い」と言われる由来があります。
本記事では、大晦日に早く寝てはいけないとされた理由と、どうしても眠りたい人の工夫について解説します。
そもそも大晦日とはどんな日?
私たち日本人にとって大晦日は、子どものころから当たり前に使われている言葉です。
「深い意味まで考えたことはない」という方がほとんどだと思います。
大晦日は、元旦に年神様をお迎えする準備をする日。
年神様とは稲の豊作をもたらす神様とされていて、食べるものに困ることなく暮らせるようにと、大切にされてきました。
また年神様は各家庭を訪れることから、ご先祖様の霊と考える教えもあるそうです。
大晦日から元旦は、神様がやってくる大切な期間であることがわかりますね。
大晦日に早く寝ると・・・。やってはいけない理由
大晦日に早く寝てはいけないと言われている理由は、「年籠り(としごもり)」という習わしが由来しています。
年籠りとは元旦の日の出まで眠ることなく、年神様の訪れを待ち、向かい入れる風習です。
このことから大晦日に早く寝るということは、年神様に失礼な行いとされていました。
「生命力が衰える」「しわや白髪が増える」とも言われていたようです。
なんだか少し怖い言い伝えですが、対処法もあります。
「稲積む(いねつむ)」と言って眠り、起きた時に「稲上げよう」と言うと、年神様を迎え入れる神事に参加したことになるのだそう。
言葉にするだけですから、やってみる価値はあるかもしれません。
一晩中起きているなんて、習わしをきちんと守られている方たちはすごいですね!
元旦は日の出の時間も遅いですし、想像するになかなか大変なのではないでしょうか・・・。
私は早く寝るタイプなので、今年の大晦日はおまじないだと思って「稲積む」を言ってから眠ろうと思います(笑)
大晦日に早く寝たい人のための工夫
稲積みの言葉を活用する
どうしても大晦日に夜更かしができない人は、「稲積む」と唱えてから寝て、起きたときに「稲上げよう」と言うことで年神様を迎え入れる習わしにあやかりましょう。
おまじないのように実践できるため、子どもや高齢者にもおすすめです。
家族と一緒にカウントダウンだけ参加
夜更かしが苦手でも、家族で「年越しの瞬間」だけ共有してから休むのも立派な参加方法です。
年神様を迎える象徴的な時間を体験しつつ、自分の体調も守ることができます。
翌朝の初日の出を大切にする
大晦日に眠ってしまっても、元日の朝に初日の出を拝むことで年神様とのつながりを感じられます。
夜更かしが難しい人は「元旦の朝に気持ちを込める」という方法で補いましょう。
大晦日にすると良いこと!
掃き納め
年末に行う大掃除とは異なり、家の中を軽くふき掃除することを指します。
大掃除は大晦日の前日までには済ませておきましょう。
掃除には厄を落とすという意味があります。
家の中を綺麗にするには絶好の機会ですから、年末の大掃除はぜひ取り組みたいですね。
年越しそばを食べる
細くて長いそばは、長寿の象徴とされています。
そばを食べることで「寿命を延ばせますように」という願いが込められているのですね。
またそばは切れやすいため、「悪縁や苦労を断ち切る」という意味もあるのだとか。
そばが苦手な方には「年越しうどん」や「年越しラーメン」などもおすすめです!
ぜひお好きな麺類を食べて、大晦日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
お風呂に入る
お風呂に入ることは体を洗い清めるという意味があります。
大晦日に入るお風呂は「年の湯」と言われていたそうです。
一年の汚れと一緒に厄も落とすという意味が込められいます。
大晦日に早く寝るのはNG!?やってはいけないと言われる理由とは?【まとめ】
いかがでしたでしょうか。
大晦日は、日本の古くからの風習がたっぷり詰まった大切な一日であることがわかりましたね。
元日の朝まで起きているのは難しいかもしれません。
しかし年神様の儀式の存在や意味を知ることで、大晦日に対する気持ちも深まったのではないでしょうか?
一年最後の日、ぜひ「大晦日にすると良いこと」を実行し、すっきりとした気持ちで新年を迎えたいですね。