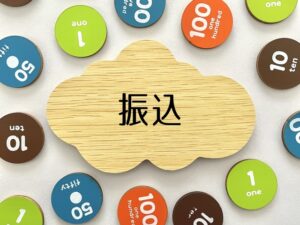年末の風物詩といえば「餅つき」。
でも「いつやるのが正しいの?」「ダメな日はあるの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
実は餅つきには縁起を担いだ日取りの考え方や地域のしきたりがあります。
この記事では、餅つきの最適な日や避けるべき日、意味や由来をわかりやすく解説します。
年末の「餅つき」に日にちは、いつ頃までに行うの?
餅つきは「新年を迎えるための準備」の行事で、年末に行うことが一般的です。
具体的に、年末とは、12月25日から31日までを指しますが、餅つきは28日までに行うのが良いとされています。
私の祖父母は米農家だったので、小さい頃は、年末になると祖父母宅の土間で電動の餅つき機で餅をついていたのを覚えています。
今でも米農家の親戚宅では、年末についた餅をきな粉餅にしてお裾分けしてくれます。
年末に行う餅つきの意味とは?
そもそも餅つきはお正月飾りの鏡餅を作るために年末に行う行事なのはご存知でしたか?
鏡餅を飾ると良い日が28日といわれています。
なぜ、鏡餅を28日に飾るのが良いとされているかというと、28の8=「八」は、「末広がり」(または「末広」(すえひろ))といって、“しだいに栄えること”との意味があり、縁起が良いとして結婚式などのお祝いごとでよく使用されています。
また、「八」という数字は日本において、昔から幸運の数字ともいわれています。
このようなことから、餅つきは、25日から28日の間に行うことが良いといえるでしょう。
「餅つき」をしてはいけないダメな日ってあるの?!
28日までに餅つきを行うのは良いとしましたが、では反対に「餅つき」をしてはいけないダメな日というのはあるのでしょうか。
その日とその意味を調べてみましたのでご紹介します!
「餅つき」を行ってはいけない日として、29日は避けた方が良いといわれています。
なぜなら、29の9は、「苦」を連想させるとのことからあまり縁起が良くないとされているためです。
また、31日の大晦日(おおみそか)に行うこともおすすめしません。
なぜなら31日に行うことを「一夜飾り」といわれ、鏡餅をそもそも31日に飾ることが、あまり縁起が良くないといわれています。
厳密に「餅つき」をしてはいけないダメな日というよりも、「縁起が良くない日」が29日と31日の大晦日とされていることは覚えておくとよいでしょう。
ちなみに、喪中の時の行事ってどこまでしていいのか悩む人は多いのではないでしょうか。
例えば、年賀状の場合は、一年以内に家族内で不幸があった場合、「喪中はがき」といって「年始のご挨拶を遠慮させていただきます」と周りに知らせるマナーもあります。
このように、日本には喪中の時にしてはいけないことのマナーや、その地域による風習、マナーが根付いているところもあります。
では、新年を迎えるための行事である「餅つき」は行っていいのものなのか気になりますよね。
結論からいうと、厳密に喪中の時の年末に「餅つきをしてはいけない」という決まりはないようです。
喪中は、「故人を偲ぶ(しのぶ)期間です。
大体、両親(実父母や義父母、養父母)であれば約12カ月、子どもの場合は3カ月から12カ月の期間はなるべく晴れがましい事や派手な行動は避けた方が良いといわれています。
そのため、お正月飾りや年始の挨拶、神社仏閣への初詣を控えるのが一般的です。
もちろん、年末の餅つきは新年を祝う準備で、鏡餅を作る準備でもあるので餅つきを避けた方が良いと考える人もいるでしょうが、喪中で大切なことは「故人」を偲び、心の中で懐かしみ、想うことです。
その家庭の事情や地域の風習やマナーに寄るところもありますので注意した方がよいでしょう。
お住いの地域でどんな様子なのか、ご家庭で話し合いをされるのがベストかもしれません。
豆知識!鏡餅の最適な場所ってどこ!?鏡餅の飾り方や意味もご紹介!
本来、年末の餅つきは正月飾りの鏡餅を作ることが目的です。
そこで、最後に豆知識として鏡餅を飾る場所や食べ方についてご紹介します!
年末に作られたお餅で鏡餅を作ります。
鏡餅は、大小のお餅に蜜柑というイメージがあると思いますが、これにも意味があります。
まず、重ねた大小のお餅には“重ね重ね良いことがありますように”という願いがあります。
その大小のお餅を半紙の上に載せて「三方(さんぽう)」という台に載せます。
(三方とは、3つの側面に穴のある四角形の台のこと。)そして、お餅の上に蜜柑をのせますが、これを「橙(だいだい)」といい、“家が代々栄えること”を意味しています。
その上に寿と書いた「扇(おうぎ)」“家族が末長く繁栄できるように”という願いが込められたものをのせて、鏡餅の完成です。
鏡餅を飾る場所は、本来、床の間や神棚が良いといわれていますが、この令和の時代ではなかなか床の間や神棚があるお家は少ないでしょう。
もしも無い場合は、家の中で一番広い部屋(リビング)や玄関、台所に飾るのが良いでしょう。
最後に、年末年始中飾っていた鏡餅っていつ食べるのか気になりますよね。
これにもちゃんとした1月11日の「鏡開き(かがみびらき)という行事があるのです。
「鏡開き」とは、年神様にお供えしたお餅を食べることで神の力を分けてもらう行事で、「開き」とは“運を開く”という願いが込められているそうです。
この「鏡開き」に、鏡餅を割ってお雑煮やおしるこにして食べるのが習わしです。
日本では昔からお餅は、神聖な食べ物として扱われ、パワーフードとされてきた歴史があります。
今でも、お餅が入ったうどん「力うどん」がありますよね。
詳細は控えますが、これはそのパワーフードであることが由来しているそうです。
そのため、鏡餅も年神様にお供えした神聖なお餅なので、お餅を割る時には刃物で切ることはしません。
手や木槌などで叩いて割るのが正しい割り方になります。
鏡開きの時は、ぜひ瓦割りが得意な人、腕力がある人、または木槌を用意しておいてくださいね。
餅つきの日取りを選ぶときの豆知識
餅つきは「吉日」を意識するとさらに安心
餅つきを行う日に「大安」や「先勝」などの六曜を気にする家庭もあります。
特にお正月準備の一環なので、大安や友引など縁起が良い日を選べば気持ちよく準備できます。
30日はどうなの?
「29日=苦」「31日=一夜飾り」として避けられますが、30日は地域によって解釈が分かれます。
特に問題ないとする所も多いので、どうしても28日までにできない場合は30日に行うのも一案です。
餅つきの回数は「奇数」が縁起良し
昔は「三升・五升・七升」と奇数でつくのが縁起が良いとされてきました。
現代では量よりもイベント性が重視されますが、こうした豆知識を取り入れると行事がより楽しくなります。
年末の餅つきをする日っていつが最適?【まとめ】
今回餅つきについて下記のことを解説してきました。
餅つきの目的やその意味には、理由や願いがちゃんと込められています。
このような日本の伝統ある行事を大切に行うことを私たちは忘れてはいけませんね。
もちろん、時代に変わっていきますので、その時代に合わせて行事を行うことも大切なことかもしれません。