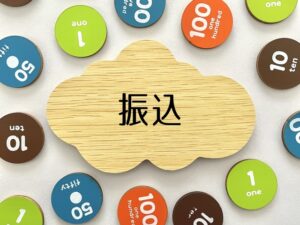大晦日といえば「1年の汚れを落として新年を迎えるためにお風呂に入る」と思う人が多いですが、一方で「大晦日は風呂に入らない」という風習があるのをご存じですか?
お風呂の神様を休ませるため、あるいは福を流さないためなど、入浴を避ける理由には日本独自の文化が息づいています。
本記事では、大晦日や元日に風呂に入らない意味や由来、現代にどう取り入れられているのかを解説します。
大晦日に風呂に入らない風習があるって本当?
日本人にとってお風呂とは昔から特別なものです。
外国では湯船がないところもありますが、日本で湯船がない家庭は滅多にないのではないでしょうか?
そんな特別なお風呂ですが、昔は家にお風呂がなく銭湯に行く人も多かったはずです。
しかし、時代と共にお風呂がない家庭は減っていきました。
自宅にお風呂があれば、当然毎日お風呂に入る人も増えてきます。
今ではお風呂は毎日入るのが当たり前になりました。
大晦日にお風呂の神様・火の神様を休ませてあげる
そこで、毎日使うお風呂だからこそお風呂の神様を休ませてあげるために。
そして昔は火でお風呂を炊いていたため、火の神様を休ませてあげるために。
大晦日に風呂に入らない風習が出来たそうです。
この風習は地域ごとにというよりは、各家庭の考えが大きいそうです。
大晦日だからこそ1年の垢や汚れを綺麗に落として新年を迎えるべきだ!という考えの人。
1年間毎日使ったものだから大晦日だけはお風呂の神様や火の神様を休ませてあげるためにお風呂に入らないべきだ!という考えの人。様々なようです。
昔から大晦日に風呂に入らないように!と育った方は未だに大晦日に風呂に入らない方も多いのではないでしょうか?
昔からの伝統が続くのは良いことですね。
また、初めて聞いた!という方もいるのではないでしょうか?
今まで通り大晦日には風呂に入って綺麗にしてから新年を迎えたい!という人は風呂に入るも良し。
今までは毎年大晦日に風呂に入っていたけど神様を休ませるためなら今年からはやめよう!という人は風呂に入らないもよし。
新たに風習として取り入れてみても良いですね。
元日に風呂に入ってはいけない理由とは?
大晦日同様、元日にも風呂に入ってはいけないという風習がある家庭もあるそうです。
元日に入ってはいけない理由は、福を洗い流さないため。だそうです。
初詣などに行き新年についた福をお風呂に入って流してしまわないように。という考え。
確かに!その考えにも納得出来ます。
また、風呂に入っても良いけど風呂を洗ったり洗濯をすると福が洗い流れてしまうためダメとされている場合もあるそうです。
大晦日も元日もどちらも各地域や家庭での考え方によって出来た風習ですので、少しずつ違った部分があるようですね。
こちらも大晦日の時と同様に新たな風習としてゲン担ぎとして取り入れたい方は取り入れてみても良いですね。
大晦日や元日の入浴風習と現代の考え方
健康面から考える入浴習慣
昔は火を焚いてお風呂を沸かしていたため、神様を休ませる意味合いで「入らない日」が設けられていましたが、現代ではガスや電気で簡単にお湯を沸かせます。
そのため、風習を守るかどうかは家庭の考え方次第です。ただし寒い時期なので、体調を考えれば入浴で体を温めることも大切です。
家族で風習を話し合う意味
年末年始の入浴にまつわる風習は地域や家庭によって異なるため、「うちはどうしているのか」を家族で話し合うきっかけになります。
子どもたちに伝えることで、「なぜその風習があるのか」を考える良い学びにもなるでしょう。
新しい年の迎え方の工夫
大晦日に入浴して1年の垢を落とすのも、入らずに神様を休ませるのも、どちらも「良い年を迎えたい」という願いが根底にあります。
現代では入浴の仕方を工夫して、たとえば「大晦日は早めに入浴し、夜は神様を休ませる」といった折衷案をとる家庭もあります。
伝統を尊重しつつ、自分たちなりの新しい年の迎え方を考えるのも素敵ですね。
大晦日は風呂入らない風習がある!?【まとめ】
大晦日は風呂入らない!?とビックリする方もいるかもしれませんが、大晦日に風呂に入らない風習や元日に風呂に入らない風習について調べてみました!
いかがでしたか?
日本人にとって昔から特別であるお風呂だからこそ、お風呂の神様を大切にする考えや、お風呂に入って綺麗にして新年を迎えたいという考え・・
どちらも良い考えであり、良い風習ですよね。
途中でも書いたようにこの記事を読んでみて新たな風習として取り入れたい方は今年から取り入れてみるのも良いかもしれませんね!
また、子供の頃に大人が教えてくれた大切な風習。
これからも守って次の世代に繋げていけると良いですね!
良いお年が迎えられますように。