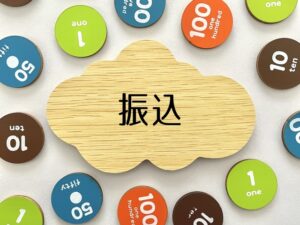年末は仏壇をきれいに整え、新年を迎える大切な準備をする時期です。
お供えの日取りや内容、のしの表書きに迷う人も多いのではないでしょうか。
本記事では「いつお供えをするのか」「のしはどう書けばいいのか」「お花や食べ物の選び方」など、年末に失礼のない仏壇のお供えマナーを詳しく解説します。
年末の仏壇のお供えはいつすればいいの?
一般的に年末の仏壇のお供えは12月28日までにするのが良いとされています。
29日〜31日は縁起が悪いため、避けた方が良いとされていますが、仕事の都合などで28日までには出来ない方も多いはず。
そんな場合は30日までにするようにしましょう。
というのも、31日は一夜飾りになってしまうため最も縁起が悪いと言われています。
ですので31日は避けて30日までにお供えをするようにしてくださいね。
そもそもお供えとはなんのために必要なの?
お供えとは年神様をお迎えするために大切な欠かせないものです。
一般的に五供と言われているものがお供えの基本となり、お正月のお供えにも五供は欠かせません。
しかし、宗派によってお供えするものや飾り付けは違ってきます。
宗派に沿ったお供えや飾り付けをするようにしましょう。
分からない場合やご両親や祖父母など聞ける方がいる場合にはその方に。
居ない場合には寺院に取り合わせると良いでしょう。
喪中の場合はどうしたら良いの?
喪中の場合は四十九日があけるまでは飾り付けなどは行わないのが一般的です。
四十九日があけた後は各ご家庭の考え方により飾り付けの有無は変わってきます。
この場合も上記は一般的な言われであり、各地域やご家庭により考え方は違います。
どうしたら良いのか分からない場合は聞くと良いでしょう。
年末のお供えののしは何て書けばいいの?
一般的には「お年賀」または「お年始」と言われていますが、これも各地域によってさまざまなようです。
「お供え」と書く場合もありますし、上記のような書き方も。
やはり、この場合もご両親や祖父母などに聞くのが間違いないと思います。
聞けるご家族が居ない方は購入するお店で聞くのもオススメですよ。
お店の方は書きなれているため、こんな書き方をする人が多いですよと教えてくれるはずです。
それを参考に決めれば間違いないでしょう。
また、お年賀やお年始と書けるのは新年を迎えた1月7日までとされています。
お花はなんでも良いの?
原則、仏壇用のお花は良いものと悪いものに分けられています。
しかし、故人がこのお花を大好きだったからどうしてもこのお花をあげたい!という場合には仏壇にはそぐわないとされているお花でも年末くらいは良いのでは?と思います。
また、仏壇のお花は近年造花でも良いとされています。
が、個人的に普段は造花でも年末くらいは生花にすると良いのでは?と思います。
自宅用ではなくお供えとしてお花を持っていく場合には生花をオススメします。
また、先程上記で故人が好きだったお花をあげたい場合は仏壇にはそぐわないお花でも年末くらい良いのでは?と書きましたが、自宅以外の場所へ持っていく場合には注意しましょう。
受け取る側がそれを承諾してくれるのであれば全く問題ありません。
しかし、一般的に仏壇には悪いとされているお花を持っていくのは失礼に当たりますし、場合によっては相手を怒らせてしまうことも。
事前に理由を説明し、許可を得てから持っていくようにしましょう。
年末のお供えで失礼しないためのマナー
のし紙の水引と表書きの注意点
お供え物を持参する際には、水引の種類にも注意が必要です。
仏事では「黒白」や「双銀」の水引を使うのが一般的ですが、年末年始のお供えでは「紅白の蝶結び」を選ぶことが多いです。
表書きは「御供」「御年賀」「お年始」など地域や宗派で異なるため、迷った場合は「御供」と書いておけば無難です。
お供えに適した食べ物
お供えには日持ちがして形が崩れにくいお菓子や果物がよく選ばれます。
特に「落雁(らくがん)」「羊羹」「みかん」などは定番です。
アルコールや嗜好品も故人が好きだったものであれば問題ありませんが、持参する場合はご家族の了承を得ると安心です。
避けたほうがよいお花やお供え
お花の場合、棘のあるバラや毒のある彼岸花は避けられるのが一般的です。
食べ物に関しても生ものや匂いが強いものは控えるのが無難です。
特に他家に持参する場合は「無難な定番」を意識し、相手に負担をかけないことが大切です。
年末の仏壇のお供えはいつすればいいの?
一般的に年末の仏壇のお供えは12月28日までにするのが良いとされています。
29日〜31日は縁起が悪いため、避けた方が良いとされていますが、仕事の都合などで28日までには出来ない方も多いはず。
そんな場合は30日までにするようにしましょう。
というのも、31日は一夜飾りになってしまうため最も縁起が悪いと言われています。
ですので31日は避けて30日までにお供えをするようにしてくださいね。
そもそもお供えとはなんのために必要なの?
お供えとは年神様をお迎えするために大切な欠かせないものです。
一般的に五供と言われているものがお供えの基本となり、お正月のお供えにも五供は欠かせません。
しかし、宗派によってお供えするものや飾り付けは違ってきます。
宗派に沿ったお供えや飾り付けをするようにしましょう。
分からない場合やご両親や祖父母など聞ける方がいる場合にはその方に。
居ない場合には寺院に取り合わせると良いでしょう。
喪中の場合はどうしたら良いの?
喪中の場合は四十九日があけるまでは飾り付けなどは行わないのが一般的です。
四十九日があけた後は各ご家庭の考え方により飾り付けの有無は変わってきます。
この場合も上記は一般的な言われであり、各地域やご家庭により考え方は違います。
どうしたら良いのか分からない場合は聞くと良いでしょう。
年末のお供えののしは何て書けばいいの?
一般的には「お年賀」または「お年始」と言われていますが、これも各地域によってさまざまなようです。
「お供え」と書く場合もありますし、上記のような書き方も。
やはり、この場合もご両親や祖父母などに聞くのが間違いないと思います。
聞けるご家族が居ない方は購入するお店で聞くのもオススメですよ。
お店の方は書きなれているため、こんな書き方をする人が多いですよと教えてくれるはずです。
それを参考に決めれば間違いないでしょう。
また、お年賀やお年始と書けるのは新年を迎えた1月7日までとされています。
お花はなんでも良いの?
原則、仏壇用のお花は良いものと悪いものに分けられています。
しかし、故人がこのお花を大好きだったからどうしてもこのお花をあげたい!という場合には仏壇にはそぐわないとされているお花でも年末くらいは良いのでは?と思います。
また、仏壇のお花は近年造花でも良いとされています。
が、個人的に普段は造花でも年末くらいは生花にすると良いのでは?と思います。
自宅用ではなくお供えとしてお花を持っていく場合には生花をオススメします。
また、先程上記で故人が好きだったお花をあげたい場合は仏壇にはそぐわないお花でも年末くらい良いのでは?と書きましたが、自宅以外の場所へ持っていく場合には注意しましょう。
受け取る側がそれを承諾してくれるのであれば全く問題ありません。
しかし、一般的に仏壇には悪いとされているお花を持っていくのは失礼に当たりますし、場合によっては相手を怒らせてしまうことも。
事前に理由を説明し、許可を得てから持っていくようにしましょう。
年末の仏壇のお供えについて!【まとめ】
お供えの日にちはおおまかに決まっているものの31日までにしていればオッケー。
また、お供えや飾り付け、喪中の時などについては各地域や家庭によってそれぞれなため一般論にとらわれず、地域や家庭の考えに沿ってすると良い。
分からない場合は確認すると良い。
お花についても原則決まってはいるが、例外もあるため、それぞれの考えに沿ってすると良い。
年越しに大切な年末のお供えをし、良いお年をお迎え出来ますように。