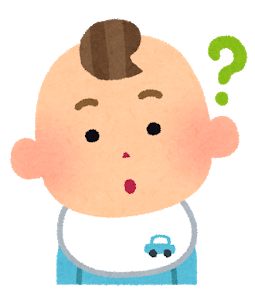お年玉を渡すとき、いとこにまであげるべきか迷う人は多いでしょう。
甥や姪ほど近い存在ではないけれど、仲良しだからあげたい気持ちもある…。
この記事では、いとこへのお年玉相場や、渡す際の注意点、家族内でのトラブルを避ける工夫を解説します。
お年玉の相場はいくら?いとこには必要?
相場について
お年玉の相場は各自それぞれなようです。
しかし、学年×1000円。
赤ちゃん〜未就学児、未就学児〜中学生、高校生以上。
といった分け方をする場合が多いようです。
あげる人ともらう人との関係性によっても値段は変わってきます。
甥や姪の場合には中学生までは5000円、高校生以上になると1万円以上。
我が子や孫の場合にも甥や姪に近いまたは+数千円といった意見が多く見られました。
普段からあまり顔を合わせることのない親戚の子供や仕事関係者の子供の場合などには5000円未満の場合も多いようです。
また、甥や姪の場合には一律5000円。
我が子、孫の場合には一律10000円。
という分け方をする家庭も一定数あるようです。
お年玉をいとこにあげるもの?注意すべきルールも解説!
いとこ同士の場合あげないことが多いようです。
しかし、お年玉は誰にあげるのか決まっている物ではありません。
年が離れていて可愛がっているいとこの場合。
年が近くて仲良しないとこで自分が社会人になったからあげたい場合。
いとこでもさまざまな場合があるかと思います。
自分がお年玉をいとこにあげたいと思うのであれば、あげれば良いでしょう。
しかし、注意したいことが2つあります。
いとこへのお年玉で迷わないための実践的な考え方
年齢・学年別の相場目安
一般的にいとこへのお年玉は甥・姪より控えめにする家庭が多いです。
未就学児は1,000円〜2,000円、小学生は2,000円〜3,000円、中学生は3,000円〜5,000円、高校生なら5,000円程度が目安とされています。
あくまで参考ですが、これを基準に家族内で調整すると不公平感が出にくいです。
家庭や地域ごとの慣習を優先する
地域や家族によって「そもそもいとこには渡さない」ケースや「兄弟姉妹の子と同じ額を渡す」など、ルールが異なります。
親世代に確認しておけば、後で「あの子には渡したのに…」と誤解されるのを防げます。
金額ではなく「気持ち」を添える工夫
小さい子には現金よりも「少額+お菓子」「図書カードや文具」などを渡すのも一案です。
金額の大小より「毎年ちゃんと覚えてくれている」という気持ちの方が大切で、親戚付き合いも円滑になります。
お年玉は相手が成人するまであげ続けるもの
1つめはお年玉は1度あげるとその人が学生の間、または成人するまでの間あげ続けなければならないということです。
その時の気分であげたりあげなかったり・・ということは一般的にはNGです。
小さい子どもの場合には先が長いため、よく考える必要があります。
この先ずっとあげるのはキツイけど今年はあげたいな。と思う場合には、お年玉として現金をあげるのではなくお菓子やおもちゃなどをお正月のプレゼントとして渡すと良いですよ。
兄弟姉妹がいる場合
2つめは自分に兄弟、姉妹がいる場合です。
自分より年下でまだお年玉をもらっている立場のきょうだいであれば良いのですが、年上だった場合には1人だけがあげてしまうと他のきょうだいが立場を失ってしまいます。
事前にいとこにお年玉をあげたい考えを伝え、相談して決めると良いですよ。
相談した上できょうだいがあげたくないのであれば、それは自由です。
気にせず自分だけお年玉をあげるようにすれば良いですよ。
また、いとこの場合にはお年玉の相場は甥や姪よりも少し安くなるようです。
これもまたそれぞれなので、甥や姪と変わらないまたは高くても自由です。
しかし、親の立場やおじさん、おばさんの立場もあります。
他の親戚の立場もあります。
色んな兼ね合いがありますので、そこを配慮した金額にすると良いですよ。
相談出来るご両親がいるのであれば、ご両親と相談して金額を決めても良いかもしれません。
ご両親からすると甥や姪なため、お年玉をあげているかと思います。
事前に自分もあげる旨を伝えておきましょう。
お年玉の相場は、いとこだといくら位?【まとめ】
お年玉の相場は?また、いとこには必要?か、調べてみました。
お年玉とはあげる人の気持ですので、金額にもあげる人にも決まりはありません。
自分があげたい人に自分があげたい金額をあげれば良いですよ。
しかし、今後のことや周りのきょうだい、姉妹、ご両親との兼ね合いもあります。
自分があげたいことを周りの方に伝えて決めるようにしてくださいね。