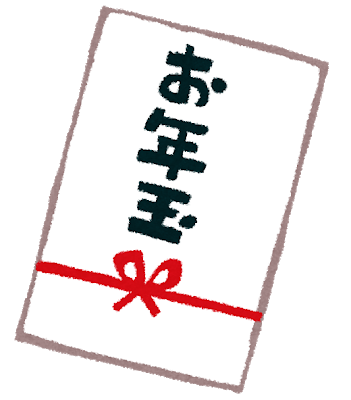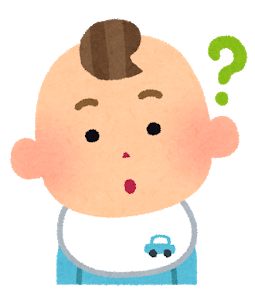お年玉をもらったとき、「お返しは必要なの?」と迷う方は多いのではないでしょうか。
祖父母、叔父・叔母、遠い親戚など、相手によって対応が変わるのが難しいところです。
この記事では、常識的なお返しの有無から、商品券や贈り物の選び方まで、状況別にわかりやすく解説します。
お年玉には「お返しが必要ない」という考え方も多い
結論から言うと、この問題には正解がなく、マナーの観点から見ても「お返しをあげるべき・必要ない」という考えが完全に二分している状況です。
決して少数派ではなく、「お返しは必要ない、子供と共にするお礼で充分」という考え方があります。いわゆる「贈り物」とは違う性質のものなので、常識的な観点から照らしても、 「むしろお返しをするべきではない」という意見すらでたりします。
結局は遠縁の親戚・金額が高額になってくれば来るほどお返しをする、パターンが多くなってくるようです。これも厳密な常識の線引きがあるわけではないようですが、「柔らかい線引き・目安」としては金額で「5000円以下程度」「叔父叔母より近縁の親戚」の場合はお返しなしで済ませるパターンが多いような状況です。
後は地域差であったり、家々の雰囲気次第になってくるので、周りに合わせていくしかないというところです。もし初めてのお年玉で感度がわからないという場合は、より近しい親戚や肉親(まずは自分の親でしょうか)に相談してみるのが無難でしょう。
お年玉のお返しで失敗しない!状況別の判断ポイント
祖父母からのお年玉は「お礼だけ」で十分
祖父母は「孫にお金を渡すのが楽しみ」という気持ちで渡していることが多く、基本的にお返しは不要です。
代わりに子供からの感謝の言葉や手書きのメッセージカードを添えると喜ばれます。
叔父・叔母など近い親戚からのお年玉はケースバイケース
金額が少額(5,000円以下)であればお返し不要とされるケースが多いです。
ただし、普段あまり会えない親戚や気を遣いたい相手には、お菓子や地域の特産品を「お年賀」として渡すと角が立ちません。
高額なお年玉や遠縁の親戚には「気持ちのお返し」を
1万円以上など高額なお年玉をいただいた場合は、3,000円〜5,000円程度を目安に贈り物をするのが無難です。
現金での返礼は避け、商品券やちょっとした品物を選び、「お正月のご挨拶」として渡せばスマートに対応できます。
お年玉に「お返しをあげる」場合は何がいいか
上記の通り、遠縁・高額になってくると、一定程度「お返し」やそれに代わるものをあげる例も多いです。この場合ですが一般的な贈り物に対するお返しの「半返し」はあまり厳密にとらえる必要がないのが一般的です。金額にかかわらず最大でも3千円~5千円くらいで済ませるのが多いイメージです。
お年玉のお返しに「現金」は基本的にはナシ
さて、お返しとしてあげるものですが、まず現金でお返しは基本的には「なし」です。一般的なお返しでもあまり行われないと思いますが、「お年玉」が現金なのに「現金」のお返しは非常識とまでは言いませんが、あまり一般的ではありません。
商品券はアリ
もし特定のプレゼントが難しいならば、商品券は選択肢の一つです。遠縁であればジャストな贈り物を渡すのもの難しいでしょうから、商品券を渡すというのは問題ありません。
また、何か贈り物をあげるのもいいでしょう。この場合は直接的にお年玉のお返しとするのではなく「お正月をお祝いするもの」として「お年賀」の名目としてお渡しすることも一案です。
これであればお年玉のお返しの意味も込めつつ、あくまで「お正月のお祝い」として贈ることができます。ちょっと変な話ではありますが、図らずも相手が「お年玉はお返しいらない派」であった場合でも「お正月のお祝い」の体とすることでリスクヘッジにもなります。
ここは個人的な感覚の問題にもなってきますが、先に書いた通り商品券も決して常識外れではないですし、問題ないです。しかし、ここで自分なりに考えた贈り物を渡すことで関係を深化していくのが付き合い上手と言える部分でもありますので、余裕があればやはり何か贈り物をお渡しすることをおススメします。
お年玉のお返しのマナー【まとめ】
お年玉は日本特有の風習で、おそらくかなり広く行われているものですが、現金を扱うので意外にセンシティブなものでもあります。
「お年玉のお返し問題」は常識に照らし合わせても正解がないものですが、親戚の関係を見ながら適切に対応していきましょう。