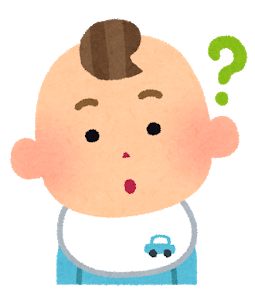「お年玉って、何歳からあげればいいの?」と迷ったことはありませんか?
赤ちゃんのうちから形式的に渡す人もいれば、小学校入学をきっかけに始める人もいます。
本記事では、0歳・3歳・小学生からあげるケースを比較し、それぞれの考え方と相場を解説します。
生まれてすぐのお正月から
誕生祝は差し上げたと思いますが、お正月に『お年玉』として、再びお祝いするのも有りかと思います。
親同士の付き合いとか、『いつからあげたらいいだろう』とか考えるのが億劫とか面倒なとき、生まれたときからあげれば、何も考えずにあげられるので助かります。
そういう人が多いのか、現代はヨチヨチ歩きの子でも首の座らない赤ちゃんにでもあげる人がいるようですね。
何歳からお年玉をあげる?お金の価値が分かる年頃になってから
今では上の『生まれてすぐからあげる』が多くなってきているとは多いますが、やはり理想的には、と言うか昔からの慣わし的には、この『お金の価値がわかる年頃になってから』と言うのが、一番多いのではないでしょうか?
価値が分からない子にあげて、お金をおもちゃにしちゃったり、間違えて破ってしまったり・・
ちょっと大きい子だと、お菓子をいっぱい買ってきてしまったり・・・
ちょっと考えただけでも、問題が起こりそうな気がします。
なので、このお金の価値が分かる年頃になってからがいいと思いますが、お金の価値が分かる年頃って何歳くらいでしょうか?
3歳はまだ分かりませんよね。
5歳か、小学校に入学してからと言うところでしょうか?
そもそも「あげない」
そもそもお年玉を『あげない』と言う選択です。
誰もがお年玉をあげて、子供の頃から大金を持つのは私もどうかなって思います。
そんな人間が他にも大勢いると思います。
ちょっとひねくれた考えかもしれませんが、子供にとっても小さいときからすべて自分の思い通りにならない事を知ることも大事だと思うので、『あげない人』ってものすごく大事かもしれませんね。
妊娠中からお年玉をあげる
そして、『これってあり?』っていう感じですが、『妊娠中から』って言うのはどうでしょう?
昔と違って、妊娠中に性別も分かるのですから、おじいちゃん・おばあちゃんは「もう可愛くて!」と言って、妊娠中にくださるかもしれませんね。
滅多にいないと思いますが。
お年玉をあげ始める年齢の考え方と実際の相場
0歳からあげる派
赤ちゃんのうちからお年玉をあげるのは「親同士の付き合いをスムーズにする」意味合いが強いです。
本人は理解できなくても、ぽち袋に少額を入れて渡すことで、形式的に「お祝い」をしたことになります。
写真や思い出としても残るので、祖父母にとっては楽しみの一つです。
3歳から・就学前にあげる派
3歳を過ぎると「お金で物が買える」ということを少しずつ理解し始めます。
この頃から少額(500円〜1,000円程度)を渡し、親が管理しながら「お金は大切に使うもの」と教えるきっかけにする家庭も多いです。
お菓子や文房具など、わかりやすいものを買わせて経験させると効果的です。
小学校入学を機にあげる派
最も多いのは「小学校入学を区切りにあげる」という考え方です。
文字や数字を理解し、周囲の友達との会話の中でも「お年玉」の話題が出る時期なので、自然に始めやすいのが特徴です。
相場としては1,000円〜2,000円から始まり、学年に応じて増やしていく家庭が一般的です
お年玉【何歳から】あげる?まとめ
調べた結果でも、やはり0歳か3歳からというのが多かったですね。
たとえ3歳でもまだお金の価値は分かっていません、あげるときは必ず親の前で渡して欲しいです。
そして、渡す相手(我が子・孫・甥っ子・姪っ子・知人の子など)によってもまた違ってくると思います。
たまにしか会わない知人の子には、その時の状況によると思います。
ただ普通、1回あげたら翌年からもあげなきゃいけない雰囲気になるので、お年玉は良く考えてあげたほうがいいと思います。
それほど付き合いもないのに、親に『お年賀』子供に『お年玉』を配っていたら、大変ですから。
さて、我が家は何歳から頂いたかしら?何歳から差し上げたかしら?と考えても思い出せません。
主人のほうには兄や姉がいたので、前例に従っていたのだと思います。
身内に前例があると楽でいいですね。
お年玉を渡す年齢に決まりがあるわけではないので、あげる本人の考えと周りの人の様子を見て決めていいと思います。
それこそどうしたらいいか分からなく迷ったときは、ぽち袋にお金を入れてバッグにしのばせ、他の人たちがあげたらあげるというように。
もちろん、その前に周りの人に相談するのがベストだと思いますが。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」と言いますので、ちょっとオーバーかもしれませんが、年齢だけではなく相場も含めて、聞かずに心配するより聞いて安心したほうがいいです。