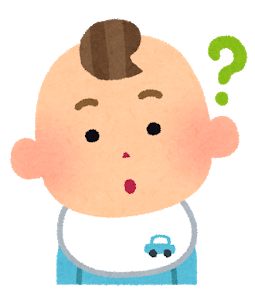お年玉はお正月の楽しい風習ですが、子どもの人数が違うと「不公平」と感じてしまうことがあります。
1人っ子と兄弟が多い家庭では、どうしても総額に差が出てしまうからです。
この記事では、そんな人数差による不公平をやわらげるための実践的な工夫や対策を紹介します。
お年玉が不公平にならないために
先程も書いたとおり、1人っ子の家庭と2人以上の家庭ではお年玉の総額に差が出てしまいます。
1人と2人だった場合にはあまり気にならないかもしれませんが、1人と5人だった場合にはどうでしょうか?
また、テレビに出ているような10人以上の子供がいる家庭と1人の家庭の場合にはどうでしょうか?
あまりにも差が大きくなりすぎて、あげる方も毎年うちの子は〇〇円なのにあげる額は、、、と思ってしまったり、もらう方もあげる額はこれだけなのにもらう額がたくさんになりすぎて申し訳なく思ってしまったり。
お互いに気持ちよくお年玉を子どもたちにあげたりもらったりすることが出来なくなってしまうことも。
そこで、何か対策がないか調べて考えてみました!
2つ紹介していきたいと思います。
相談しておく
自分や旦那さんのきょうだいや姉妹の子どもたち、つまり甥っ子や姪っ子との差が激しくなってしまう場合です。
この場合にはあらかじめ金額を相談し、決めておくと良いでしょう。
1人一律何円か。や、子供の学年や年×1000円。
もしくはきっちりと同じ額にしたいという場合は総額を決めて人数分で割るのも良いですね。
あらかじめ相談し、決めておくことでお互いに差額が気になることもなくイヤな思いをすることもなくなりますよ。
手土産などで差額分を埋める
相談しあえる関係性でない場合もあるかと思います。
自分の子どもたちが多くもらってしまうけど相談して決めておくことが出来ないときは、差額分くらいの手土産を用意すると良いでしょう。
お年玉としてはあげるよりももらう方が多くなってしまいますが、手土産として返すことでお互いにわだかまりが出来るのを避けることが出来ますよ。
もらう側も気にならなくなりますし、あげる側も気にならなくなります。
しかし、差額分以上に高価なものを手土産として持って行ってしまうと相手が気を使うことになり、意味がなくなってしまいます。
差額分と同じくらいもしくは前後くらいの値段になるようにしましょう。
人数差で不公平を感じないための追加アイデア
年齢に応じた「学年ごとの一律額」を設定する
子どもの人数で調整するのではなく、学年ごとに「小学生は〇〇円、中学生は〇〇円」とあらかじめルールを決める方法です。
これなら兄弟姉妹の数に関わらず「学年ごとの公平感」を保ちやすくなります。
親世代で「お年玉プール制度」を作る
親戚間で「お年玉は全員分をまとめてプールし、子どもたちに均等に分配する」という方法もあります。
人数が多い家庭・少ない家庭の差が気にならず、親世代も安心して渡せます。
地域や家族の雰囲気によっては採用されるケースもあります。
お金以外の「体験」をお返しにする
不公平感を埋めるのに、お金ではなく「一緒に出かける・遊ぶ・体験をプレゼントする」方法もおすすめです。
お年玉は子どもに渡しつつ、差額分は「みんなで遊園地に行こう」「スイーツを食べに行こう」と体験に変えると、物質的な差より思い出が残り、不公平感がやわらぎます。
お年玉が不公平に?【まとめ】
お年玉が不公平になってしまう対策について調べてみました!
いかがでしたか?参考になりましたか?
どうしても子どもの人数によってお年玉の総額に差が出てしまい不公平になってしまうことがあります。
仕方がないことですが、あげる側ももらう側もあまりにも差額が大きくなりすぎると気持ちよくあげたりもらったりすることが難しくなってしまいます。
そんな場合には
①あらかじめ相談して解決策を決めておく
②差額分くらいの手土産を持参する
ことで、お互いに気持ちよくあげたりもらったり出来るようにする工夫が大切です。
もらう子どもにとってはどちらも同じお年玉であり、子どもたちには差額や不公平など大人の事情は分からないし、関係ありません。
もらう子供が気を使ってしまわないように、大人が工夫してあげてくださいね。
お年玉をもらう方もあげる方も気持ちよくお正月を過ごせると良いですね!